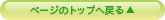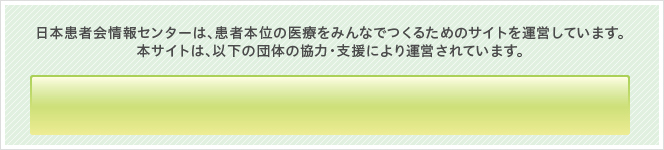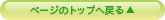トップページ>患者団体マッチングデータベース>日本肝臓病患者団体協議会(日肝協) - 患者団体マッチングデータベース
患者団体情報
概要
- 団体の運営代表者
- 中島 小波(代表幹事)
- 代表者プロフィール
- 1971年1月、東京で「肝炎の会」を設立した故中島弘道医師の妻(当事者)
- 主な活動者
- 有坂 登(代表幹事) 藤村 隆(代表幹事)
- 主な活動者プロフィール
- 長野県の「肝炎対策協議会」の患者代表。長野県難病連事務局長を兼任している 大阪肝臓友の会会長
- 団体設立経緯と目的
- 当協議会は1971年、故中島弘道医師を初代会長とした「肝炎の会」を前身とし、その後各県・地域に「患者会」が誕生するなかで、1986年5月、「全国肝臓病患者会連絡協議会」(全肝協)を結成した。1991年10月に肝臓病患者の全国組織として改組され、今日に至っている。現在、35都道府県76患者会(約8000人)が加盟している。結成当初から、ウイルス肝炎の患者・感染者は大半が集団予防接種や輸血・血液製剤等、患者自らが防ぎようのない原因で感染した「医原性の疾患」だという認識で、次の4つの基本要求を掲げて活動してきた
- 団体の種別
- 任意団体
- 設立年
- 1986年
- 支部数
- 76
- 活動範囲
- 全国
- 会員種別
- 正会員、賛助会員
- その他会員種別
- 会員数
- 約8000
- 会員の条件
- 罹患患者、罹患患者の家族、臨床医師、基礎医学の医師、看護師、コメディカル、製薬企業の関係者、マスコミ関係者
- 地域・年齢・医療機関・その他
の限定
- 個人は賛助会員のみ
- 顧問医の人数
- 0
- 顧問医の名前と肩書
-
- 活動における顧問医の役割
- 所属団体自由記入
- 日本難病・疾病団体協議会(JPA)
- 会則有無
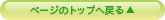
運営・活動内容
- 理事会の開催
- 年1回
- 活動理念の明文化
- あり
- 会員に対する会計報告
- 年1回
- 会費収入の割合
- 53%
- その他の収入
- 一般の人からの寄付、企業からの寄付
- 上記以外の収入
- 毎年国会請願署名と募金活動(収入の約40%)
- 会員以外で活動を特に
支援してくれる個人・団体
- 医療機関 医師(顧問医を除く)
- その他団体
- ウイルス肝炎研究財団
- 具体的な支援内容
- 「医療講演会」「相談会」等に、専門医がボランティアとして講師を引き受けてくれる。
- 会員同士の交流会の実施
- 定期的:1〜2回
- 相談事業の定期実施
- 相談件数
- 会員へのニュースレターの
発行
-
【紙】定期的:年4回
【電子メール】定期的:12回
- 会員以外からの問合せの対応
- 電話、電子メール
- その他の対応
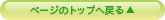
社会への働きかけ
- 調査研究事業の実施
- —
- 臨床試験への協力
- —
- その他
- —
- 患者の実態やニーズを
把握するための活動
- 患者からの相談に応じている
- その他
- 東京の会が実施している「電話相談室」月〜金10:00〜16:00の相談から
- 社会への発信
- 署名活動やデモを行っている
- その他
- 会報等を行政、肝臓学会等関係機関、マスコミ等に配布
- 医学情報の入手先
- 医学の専門雑誌、医学論文
インターネット(掲示板)
インターネット(病院、研究機関等の公開情報)
- その他
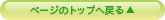
患者代表としての参加経験
学会への参加
- 所属学会
- なし
- 過去に学会で
展示や発表を行った経験
- なし
- 診療ガイドライン作成の場
への参加経験
- なし
- 診療ガイドライン作成の場
への参加の意思と理由
- 要請があれば積極的に参加すべき
医療政策への参加
- 医療政策への参加経験
- ・2002〜2005年から4年間、「肝炎等克服緊急対策研究事業」「対策研究班」に班友として参加。全国各自治体、健保組合等への肝炎ウイルス検査のアンケート調査。電話相談から見えてきた肝炎対策等を班会議で報告。 ・2005年8月に出された「C型肝炎対策等に関する専門家会議」の報告書を受けて2006年6月に「全国C型肝炎診療懇談会」に患者代表として参加。現在も継続中。3回出席(2006年中)
- 会議の種類
- 検討会、研究会
- 主催者
- 厚生労働省
- 参加の立場
- 常任の委員、その他
- 医療政策への参加の
意思と理由
- 自らアピールして積極的に参加すべき
医療機関への参加
- 医療機関の運営への
参加経験
- なし
- 種別
- 参加の立場
- 医療機関への参加の
意思と理由
- 要請があれば積極的に参加すべき
医育機関への参加
- 医育機関の教育への
参加経験
- なし
- 種別
- 参加の立場
- 医育機関への参加の
意思と理由
- 要請があれば積極的に参加すべき
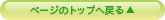
その他
- 現在特に力を入れて
取り組んでいること
- 日肝協の活動や日本肝臓学会の熱心な働きかけによって、2002年度(平成14年)から国の『C型肝炎等緊急総合対策』がスタートした。(5か年) €国民に対する普及啓発と相談指導の充実 肝炎ウイルス検査の実施 ¡治療方法等の研究開発および診療体制の整備 ¤予防、感染経路の遮断 ¡はかなり進展したが、高額な医療費負担から治療を断念する患者も多く、国に医療費負担の助成を要望している。
- 今後取り組んでいきたいこと
- 総合的な肝炎対策を推進するために、都道府県に「肝炎対策協議会」が平成19年度中に設置される。すでに10都道府県で患者会の代表が参加している。かかりつけ医と専門医療機関との連携・協力体制を整備して、患者が身近で適切な医療が受けられるよう働きかける。新たに設置される「肝炎研究センター」(千葉県・市川市)の整備や機能について患者の立場から提案をする。
- 団体の概要、活動内容が
わかるリーフレット、
メルマガ等の有無と入手方法
- 日肝協と各県患者会は本部、支部の関係ではなく、共通する患者・家族の要求実現を目指す『連絡協議会』としての性格と役割を担っている。会長は置かず、3名の代表幹事制を敷いている。毎年開催される「代表者会議」(総会)で年度の重点目標を決定して活動している。国会請願、中央省庁、各県自治体へ働きかけている。活動内容はメール、ブログ、会報等で紹介している。
- マスコミの取材を受けた
経験
- 1992年から臨時の電話相談として「肝炎110番」を年1回、主要都市を中心に医師などの協力を得て開設してきた。そのつど、マスコミの取材があった。1993年、NHKの「クローズアップ現代」の取材 東京へのインターフェロン治療難民(東京は単独事業で医療費助成)2000年から血液製剤による感染(C型)でマスコミの取材が増え、肝炎対策が大きな社会問題になった。